今日の朝刊では、以下の4つの記事が取り上げられています。それぞれの記事について、わかりやすく解説していきます。
今年の上場廃止が最多に:日本企業の新陳代謝と市場の未来
記事概要
2024年に日本の東京証券取引所で上場廃止1となる企業は、過去最多の94社に達する見込みです。これにより、上場企業数が初めて減少します。
この背景には、東証による市場改革や基準の厳格化、そして投資家からの企業価値向上の圧力が関係しています。
一方で、新規上場企業の数は伸び悩んでおり、これからの日本経済にとって重要な成長企業の育成が課題となっています。
この記事では、この現象の背景と今後の影響について詳しく解説します。
東証で進む上場廃止の背景
今年、東証で上場廃止となる企業は94社に上り、前年比で33社(54%)増加するとされています。
この増加には、以下のような理由があります。
- 市場の圧力と企業の選択
東証では市場の魅力を高めるため、2022年に市場区分を再編し、上場を維持する基準を厳しくしました。
これにより、一部の企業は基準を満たすことが難しくなり、自ら市場を退出する選択をしています。
また、株主や投資ファンドによる買収提案が活発化しており、これを契機に上場を廃止するケースも増えています。
- 上場のメリットとデメリット
上場企業は資金調達のために市場からの期待に応える必要がありますが、その一方で上場維持にかかるコストや、株主からの厳しい要求に直面します。
例えば、大正製薬ホールディングスの非公開化では、オーナー家が「上場が長期的な施策の足かせになる」と判断したことが理由とされています。
新規上場の停滞と市場の変化
今年の新規上場企業数は約80社と低調で、上場廃止企業数との差し引きで上場企業数が初めて減少します。
この現象は以下の要因に起因しています。
- グロース市場の低迷
新興企業が集まるグロース市場の活気が乏しく、企業の上場意欲が低下しています。
- 上場基準の厳格化
特に時価総額や収益性が基準に達しない企業は、上場廃止のリスクに直面しており、新規上場も慎重になっています。
欧米では、未公開市場での資金調達が広まり、企業が上場にこだわらない傾向が強まっています。
同様の動きが日本でも見られるようになりつつあるのかもしれません。
上場廃止のメリットと課題
企業が上場廃止を選択することで、以下のようなメリットがあると考えられます。
- 経営の自由度が増す
上場企業は株主への説明責任が重く、迅速な経営判断が難しい場合があります。
上場廃止により、中長期的な成長を目指した柔軟な経営が可能になります。
- 市場の質向上
東証は企業数よりも質を重視する方針を取っており、上場基準を満たす意欲のある企業が市場に残ることで、市場全体の魅力が向上する可能性があります。
一方で、課題も残ります。
- 成長企業の育成
上場廃止が進んでも、新たな成長企業がすぐに現れるわけではありません。
米国の「マグニフィセント72」に匹敵する企業が日本には少ないことも、課題として挙げられます。
日本市場と投資家の関係の変化
日本の株式市場では、「アクティビスト」と呼ばれる積極的な株主の影響力が増しています。
彼らは、企業に対して株主価値の向上や経営の透明性を求める提案を行います。
2024年にはすでに66件の株主提案があり、企業はこれに応える形での改革を進めています。
また、日本企業の株式持ち合い(※1)が減少しているため、外部からの買収提案が成立しやすくなっています。
このような状況下では、企業が市場で生き残るために、より高い経営能力が求められるようになっています。
(※1 株式持ち合い:企業同士が株を持ち合う関係)
未来への展望
上場廃止が増える一方で、上場を維持する企業には市場からの期待がますます強まります。
これからの日本市場が直面する課題には、次のようなものが考えられます。
- 成長を促す仕組みの構築
優秀な人材や技術を持つ中小企業が成長できる環境を整えることが重要です。
- 投資家との良好な関係作り
企業が株主に説明責任を果たしつつ、自らのビジョンを実現するためのバランスを取る必要があります。
- 新興市場の活性化
グロース市場が活気を取り戻すことで、新しい企業が次々と誕生する可能性が広がります。
まとめ
日本の上場廃止企業数が増加し、上場企業数が初めて減少するという現象は、企業の新陳代謝が進む一方で、成長企業を育てる土壌を整える必要性を浮き彫りにしています。
市場改革や投資家との関係変化が進む中、日本企業が世界に通用する競争力を持つためには、経営の質と投資家からの信頼を高める努力が求められています。
韓国大統領の事情聴取問題と弾劾後の米韓同盟の行方
記事概要
韓国の尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領は、内乱と職権乱用の疑いで検察から出頭を求められましたが、これに応じていません。
これを受けて検察は再度召喚を通知する予定です。
また、尹氏の弾劾訴追を受けて首相が代行を務める中、米国との同盟維持を確認するため、バイデン大統領と電話協議が行われました。
この記事では、尹氏をめぐる事情と韓国国内外の動向についてわかりやすく解説します。
尹錫悦大統領への出頭要請とその背景
韓国検察は尹錫悦大統領に対し、事情聴取のため出頭を要請しました。
この理由は、尹氏が非常戒厳を宣言したことにより、内乱罪や職権乱用の疑いがかけられているためです。
非常戒厳とは?
非常戒厳は、国家が極めて混乱した場合に、軍が直接指揮を執り、治安を維持する措置です。
しかし、民主主義国家では、軍が政治や司法に過度に介入するリスクがあり、これが問題視されることがあります。
出頭要請に応じなかった尹氏
検察は12月15日に出頭するよう求めましたが、尹氏はこれに応じませんでした。
このため、検察は再度召喚を通知し、場合によっては逮捕状を請求する可能性も示唆しています。
韓国憲法では、大統領には不逮捕特権が与えられていますが、内乱罪に関しては例外となります。
もし尹氏が逮捕されれば、現職大統領が逮捕されるのは韓国史上初のこととなります。
大統領弾劾訴追と現在の職務代行
尹氏は国会による弾劾訴追案の可決により、現在職務停止中です。
その間、大統領職は韓悳洙(ハン・ドクス)首相が代行しています。
このような事態は、韓国の政治や国際関係に大きな影響を与えています。
弾劾訴追とは?
弾劾訴追は、特定の公職者が憲法や法律に違反した疑いがある場合、国会がその職務を停止し、最終的な裁判所の判断を待つ制度です。
韓国では過去に朴槿恵(パク・クネ)元大統領も弾劾訴追され、職務を解任されています。
米韓同盟の維持をめぐる電話協議
大統領代行を務める韓首相は、バイデン米大統領と16分間の電話協議を行い、米韓同盟の維持を確認しました。
これは、韓国国内での政治的不安定が、外交や安全保障に影響を及ぼすのを防ぐための重要な取り組みといえます。
米韓同盟とは?
米韓同盟は、1953年に締結された韓国とアメリカの安全保障協定を基盤としたもので、北朝鮮に対する抑止力として機能しています。
両国は軍事面だけでなく、経済や技術分野でも深い関係を築いています。
電話協議でのポイント
韓首相は、「全ての国政が憲法と法律に基づいて行われる」と説明し、米国側の懸念に応えました。
また、外交・安全保障政策において、米韓同盟が揺らぐことなく進められるよう努力することを強調しました。
この発言は、韓国政府として米国との関係を重視する姿勢を示しています。
検察と政府の今後の動き
検察は尹氏の出頭がない場合、さらなる法的措置を取る可能性があります。
これには逮捕状の請求も含まれるため、今後の展開が注目されています。
一方で、韓国政府は国内外の安定を維持しつつ、米国との強い同盟関係を再確認する姿勢を示しており、外交的な不安定を避ける努力が続いています。
国際的な影響と韓国国内の課題
この問題は韓国国内だけでなく、国際的にも注目されています。
特に、アメリカとの同盟関係や北東アジアの安全保障に影響を与える可能性があります。
また、韓国国内では、大統領職務停止という異例の状況を受けて、政治的安定をどう確保するかが課題となっています。
今後の見通し
尹氏の事情聴取問題は、韓国の政治や司法制度にとって重要な試金石となります。
また、米韓同盟を中心とした外交政策がこの混乱の中でどのように進むかも注目されています。
韓国政府と検察がどのような判断を下すか、そして国際社会がこれをどう見るかが、今後の焦点となるでしょう。
この記事に関連する、韓国大統領の非常戒厳の背景や現在までの流れが気になる方はこちら👇️
自衛官、防衛産業に再就職しやすく:政府が処遇改善策を検討
記事概要
政府は、自衛官が退職後に防衛産業や関連企業への再就職をしやすくする制度を新たに設ける方針を示しました。
この取り組みは、自衛官の処遇改善と人材確保を目的としています。
自衛官は一般的な民間企業と比べて早い時期に定年を迎えるため、退職後の生活への不安が課題となっています。
この問題に対応するため、再就職支援を強化し、防衛産業などの需要に応じた人材供給も図ります。
具体的には、関連団体との協力体制を構築し、企業とのマッチング機会を増やす予定です。
自衛官の処遇改善が重要視される理由
自衛官は、国防という特殊な任務を担う職業でありながら、民間企業と比較して早い段階で定年を迎えます。
例えば、階級によりますが、多くの自衛官は50代半ばから60歳前後で退職することが一般的です。
一方、民間企業では定年延長が進み、65歳以上でも働き続ける人が増えています。
そのため、自衛官の退職後の生活に対する不安が広がっています。
政府がこの問題に対応しようとする背景には、自衛官のなり手不足が深刻化している現状があります。
若い世代が自衛官を職業として選ぶ際、退職後のキャリアの不透明さが大きな障壁となっています。
処遇改善策は、この障壁を取り除き、人材を確保するための重要な手段と考えられます。
防衛産業と自衛官再就職の関係性
防衛産業は、自衛隊の装備品や関連技術を提供する重要な役割を果たしています。
そのため、自衛官としての経験を活かせる職場としても適しています。
特に、自衛官は装備品の操作や整備に関する高度な知識を持っており、退職後に防衛関連企業でその知識を活用することが可能です。
防衛産業側にとっても、こうした経験者を採用することは、製品開発やメンテナンスの効率化に繋がるため、大きなメリットがあります。
政府は、この相互利益を踏まえ、防衛関連企業と協力し、自衛官の再就職を支援する仕組みを整備しています。
再就職支援制度の具体的な内容
政府が検討している再就職支援制度には、以下のような取り組みが含まれます。
- 企業との協力体制の構築
防衛関連企業で構成される「日本防衛装備工業会」と協力し、自衛官の再就職を支援するための文書を締結する予定です。
この文書では、企業側が再就職に協力する方針を示し、自衛官にとって受け入れ体制を整えることが求められます。
- マッチング機会の拡充
防衛省と経済産業省が連携し、退職後の自衛官と企業を結びつけるマッチングイベントやプログラムを増やします。
これにより、自衛官は自分のスキルを活かせる職場を探しやすくなります。
- 防衛産業以外の分野への支援
航空宇宙産業や建設業といった他の産業にも再就職の道を広げることを目指します。
これらの分野では、自衛官が培ったリーダーシップや組織運営能力が重宝されることが期待されています。
処遇改善策がもたらす影響
この新しい制度が導入されれば、自衛官の生活基盤が安定し、現役自衛官のモチベーション向上に繋がる可能性があります。
また、若い世代が自衛官を職業として選びやすくなり、深刻化する人材不足の解消に貢献するでしょう。
さらに、防衛産業では経験豊富な人材を確保できるため、製品の品質向上や技術革新が期待されます。
結果的に、国家防衛力の向上にも繋がると言えます。
今後の展望
政府は2025年までに再就職支援制度を本格的に導入する計画です。
その際には、関連団体や企業との緊密な連携が鍵となります。
また、再就職に関する情報提供の充実や、退職後の教育プログラムの拡充も必要とされるでしょう。
今回の取り組みは、自衛官の処遇改善だけでなく、日本全体の防衛力強化にも繋がる重要な政策です。
これを機に、自衛官の仕事や役割について社会全体で理解を深めるきっかけになることが期待されます。
中小企業の新しい承継の形:親族以外に託す未来の可能性
記事概要
少子化が進む中、中小企業では後継者不足が深刻な問題となっています。
しかし、親族以外への事業承継が増加することで、この課題に対応しようとする動きが広がっています。
内部昇格や外部人材の起用、さらにはM&A(合併・買収)による承継も選択肢に加わり、企業の柔軟な代替わりが新たな成長の可能性を生み出しています。
この記事では、日本の中小企業の新しい承継の形について解説します。
事業承継とは?
会社の経営権や事業を後継者に引き継ぐことを指します。
これには、経営権(株式)だけでなく、人材、ノウハウ、資産などの経営資源も含まれます。
事業承継の主な種類は以下の3つです。
- 親族内承継:
経営者の子どもなど、親族に事業を引き継ぐ方法。
- 親族外承継(社内承継):
会社の役員や従業員など、親族以外の社内の人材に事業を承継する方法。
- M&A:
他社との合併や買収により、第三者企業に事業を引き継ぐ方法。
事業承継の目的は、会社の存続と発展を確保することです。
特に中小企業では、経営者の高齢化や後継者不足が問題となっており、早期に事業承継の準備を進めることが重要です。
事業承継では、以下の3つの要素を総合的に引き継ぐことが重要とされています。
- 会社の経営権
- 資金や資産
- 経営理念などの知的資産
親族以外の後継者が増える背景
これまで、中小企業の事業承継は親族間で行われることが一般的でした。
特に創業家は「家業」という意識が強く、家族が事業を引き継ぐケースが多かったのです。
しかし、少子化が進む中で、後継者となる家族がいない、あるいは承継を希望しない場合も増えています。
このような状況が「親族以外の後継者」を増やす背景となっています。
例えば、丸ヱム製作所では親族の中に適任者がいないため、社内で実績を積んだ石本氏が後継者に選ばれました。
このケースは、内部で育った社員に経営を託す「内部昇格型」の承継が進んでいる例の一つです。
内部昇格と社員のモチベーション
親族以外の社員が社長に昇格することは、従業員全体のモチベーション向上にもつながります。
「実績次第で誰でも社長になれる」というメッセージは、会社全体の成長意欲を刺激します。
例えば、技術承継機構では、買収した企業で内部昇格を積極的に進めています。
帝国データバンクの調査によれば、2024年には内部昇格型の承継が初めて親族間の承継を上回りました。
このことは、企業の承継方法が柔軟化している証拠といえます。
M&A(合併・買収)による承継の可能性
内部昇格に加え、近年ではM&Aによる承継も増えています。
M&Aとは、他の企業がその会社を買収したり、合併したりして事業を引き継ぐ方法です。
この手法は後継者不在の中小企業にとって有効な選択肢となっています。
2024年には、M&Aによる承継が全体の20%を超えました。
ショーワグローブでは、創業家が株を保有したまま外部の専門家を招いて経営を任せる形を取りました。
こうした外部人材の起用は、企業の視点を広げるだけでなく、特定の課題解決にも効果的です。
例えば、米国事業の立て直しを専門家である星野氏に委ねた結果、経営の安定化を目指すことができました。
柔軟な承継がもたらす成長の可能性
事業承継が企業の成長にどのように影響するのかについては、データでも明らかです。
東京商工リサーチの調査によれば、事業承継を実施した中小企業は、実施しなかった企業と比べて、純利益の成長率が平均で約6倍に達しました。
このデータは、柔軟な承継が企業の将来に大きな可能性をもたらすことを示しています。
また、時代や状況に応じて親族、生え抜き社員、外部人材のいずれもが社長になれる体制を整えることが重要とされています。
これは単に後継者問題を解決するだけでなく、企業のイノベーション(革新)を促進する可能性を高めます。
大廃業から大承継へ
日本では、後継者不在による「黒字廃業」が課題として指摘されてきましたが、多様な事業承継の形が広がることで、この危機を乗り越えることができるかもしれません。
少子化という大きな社会的課題に対応しつつも、企業ごとの状況に応じた柔軟な承継の仕組みが、日本の経済基盤を強化する鍵となるでしょう。
未来に向けた事業承継は、単なるバトンの引き継ぎではなく、企業の新たな成長の土台を築くチャンスでもあります。
この流れがさらに広がれば、日本の中小企業が持続的に成長し、社会全体にもポジティブな影響を与える可能性があります。
全体のまとめ
私たちへの影響と今後の考え方
これらの出来事は、経済、国際関係、そして社会のあり方がそれぞれ密接に関連していることを教えてくれます。
変化が激しい時代において、私たちが考えるべきことは次の通りです。
- 柔軟性を持つこと:
企業の経営やキャリア選択、国際情勢への対応など、時代の変化に応じて柔軟に考え、行動する力が求められます。
例えば、進路や仕事を選ぶ際には、長期的な視点で新しい産業やスキルに目を向けることが重要です。
- 情報を知ること:
ニュースや社会の動きにアンテナを張り、背景や原因を深く理解することが必要です。
情報が断片的だと、偏った考えや誤解を招きやすくなります。
- 協力と調和を目指すこと:
国際関係や防衛産業のように、利害が対立する場面でも、調和を目指した解決策を考えることが大切です。
これは日常生活でも、人と意見が違うときに活用できる視点です。
未来を見据えた経済と社会の可能性
経済や社会、国際情勢の動きは複雑ですが、その中には未来へのヒントが隠されています。
企業が柔軟な承継を実現し、国が人材や資源をうまく活用できれば、社会全体の活力は高まります。
個人としても、変化を恐れず、新しい知識を学び続けることが、これからの時代を生き抜く力になるでしょう。
新しい知識を学ぶには、まずお金に対する知識を身につけることをおすすめします。
しかしお金の知識に関して、学校でも社会でも誰も教えてくれません。
ではどうやって学んでいけばいいのでしょうか?そんなときにおすすめな方法がこちらです👇️
ポイントとなる用語解説
- 上場廃止
金融商品取引所に上場している企業の株式が、取引所での取引対象から外れることを指します。上場廃止後も株主の権利(議決権、配当請求権など)は残りますが、取引所での売買はできなくなります。上場廃止には、資金調達の制限やブランド価値の低下などのデメリットがある一方で、経営の自由度向上やコスト削減などのメリットもあります。 ↩︎ - マグニフィセント・セブン(Magnificent Seven)
米国株式市場を牽引する7つの主要テクノロジー企業を指す総称です。
Google (Alphabet)、Apple、Meta (Facebook)、Amazon、Microsoft、Tesla、NVIDIA、この7社です。 ↩︎







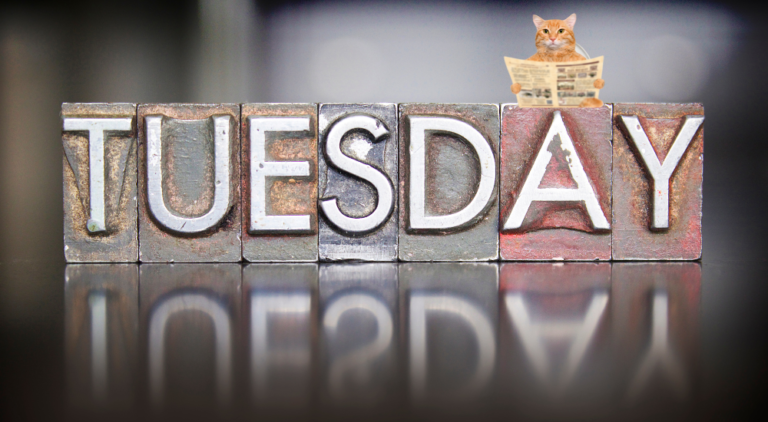






コメント